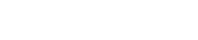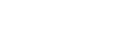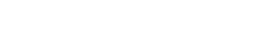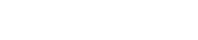【強み・特色1:ロボット支援手術】
手術支援ロボットであるダヴィンチは米国のインテュィティブサージカル社が開発したロボット支援手術機器です。患者さんの身体的な負担が少ない腹腔鏡手術の特長を生かしつつ、ロボットの支援により従来難しかった手術操作が可能になりました。ダヴィンチによるロボット支援手術では、医師がモニターに映し出される鮮明な3次元画像を見ながら、ロボットのアームについている鉗子やカメラを遠隔操作します。これにより、安全で精密な手術が可能となり手術成績の向上が期待されています。ダヴィンチのみで手術が行われるわけではなく、あくまでも術者の手指の動きを再現する“手術支援”のためのシステムであり、患者さんの脇に助手の医師と看護師がついて補助を行い、協調して手術が行われます。

当科では2012年4月に保険適応となった前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘除術を2013年から開始したことを皮切りに、他のロボット支援手術術式が適応追加になるたびに導入し、現在では泌尿器科領域で保険適応となっているすべての術式(腎癌に対する腎部分切除術および腎全摘除術、上部尿路癌(腎盂癌・尿管癌)に対する腎尿管全摘除術、副腎皮質腫瘍および副腎髄質腫瘍に対する副腎摘除術、膀胱癌に対する膀胱全摘除術および回腸導管造設術、腎盂尿管移行部狭窄症に対する腎盂形成術、骨盤臓器脱に対する仙骨腟固定術)に対応している県内随一の施設となっています。

【強み・特色2:女性骨盤臓器脱診療センター】
当科では2021年4月に女性泌尿器専門外来を開設し、骨盤底筋の緩みにより生じる女性特有の疾患である骨盤臓器脱や尿漏れを積極的に診療してきました。しかし、これらの疾患は泌尿器科と婦人科の境界領域にある疾患で、患者さんはどの科を受診したらいいのか迷われることが多いかと思います。
そこで、当院では2023年4月に九州地区の大学病院初となる「女性骨盤臓器脱診療センター」を設置し、以前は骨盤臓器脱に対して泌尿器科と婦人科がそれぞれ個別に対応していましたが、外来での診察・診断、治療、その後のフォローアップを泌尿器科医師、婦人科医師が一緒に診療することでより良い医療を提供できる環境が整いました。
女性骨盤臓器脱診療センターでは主に下記疾患に対する診療を行っております。
| 女性骨盤臓器脱診療センター設置後の手術件数(2023年4月~2024年12月) | |||
|---|---|---|---|
| NTR | 6例 | ||
| TVM | 28例 | ||
| 仙骨膣固定術 | 腹腔鏡下 | 6例 | 13例 |
| ロボット支援下 | 7例 | ||
| 中部尿道スリング手術 | 6例 | ||
| 膀胱膣瘻修復術 | 1例 | ||
1,骨盤臓器脱
骨盤内の臓器は骨盤底筋と呼ばれる骨盤を支える複数の筋肉で支えられています。骨盤臓器脱はそれらの筋肉が緩み、臓器を支えられなくなり生じます。脱出する部位により、膀胱瘤、子宮脱、直腸瘤などに分類され、会陰部の違和感や下垂感、排尿困難感、尿漏れ、排便障害などさまざまな症状が出現します。腹圧をかけた時や夕方に重力の影響で症状が悪化し、生活の質の低下につながることが多いです。
外来では問診票での症状の確認や内診台での視診・内診、エコー検査で診断を行います。
治療方法は大きく分けて手術療法と保存的治療の2つがありますが、脱の程度や年齢、併存疾患の有無など患者さんの生活スタイルや状態に応じて決定します。

① 手術療法
・メッシュを使わない従来法(NTR:Native Tissue Repair)
以前から行われている方法で、メッシュを使わない手術です。腟から子宮を摘出する方法や下がっている子宮を靱帯に固定する方法などがあり、お腹を切らずに、短時間で行うことができる手術です。人工物を使用しないため合併症の心配は少ないですが、ほかの術式に比べ再発する可能性があります。
・経腟メッシュ手術(TVM手術:Tension-free Vaginal Mesh)
腟からメッシュと呼ばれる網目状の医療用合成シートを挿入し、ハンモック状に敷くことで弱くなった骨盤底を支えて修復を行う方法です。お腹を切らずに短時間で行うことができ、他疾患で長時間の手術が難しい場合でも治療が可能です。脱の程度次第では再発率も少ない方法です。

・仙骨腟固定術(腹腔鏡手術・ロボット支援下手術)

腹部に1cm程度の小さな穴を数か所あけ、子宮を切除した後、メッシュを腟の全長を覆うように置き、それを仙骨に固定する方法です。2014年に腹腔鏡手術、2020年にロボット支援下手術が保険適応となりました。ほかの方法より手術時間が長い、腹部に創部が残るといった弱点はありますが、腟から行う手術よりも再発率が低い、出血量が少ない、術後も性交渉が可能といったメリットがあります。
② 保存的治療
・骨盤底筋体操
軽症の場合は臓器が下がる程度が軽くなる効果があります。
・ペッサリーリング / サポート下着
臓器が下がってくるのを防ぐ装具を使用し、症状の軽減が期待できます。
2,尿漏れ
尿漏れにはおなかに力が入った時(運動や重いものを持った時など)に漏れる腹圧性尿失禁と、急に強い尿意がきてトイレに間に合わずに漏れてしまう切迫性尿失禁の2種類があります。それぞれ病態が違い治療方法も異なるため、問診票で漏れる時の状況や漏れの量を確認し、エコー検査などをおこない診断します。
①腹圧性尿失禁
骨盤底の筋肉が緩み、膀胱や尿道を支える力が弱くなり尿道がぐらつくことで生じます。
・骨盤底筋体操
軽症の場合は尿漏れの改善を期待できます。
・中部尿道スリング手術

保存的治療で十分な効果が得られない場合は手術の適応となります。 1cm幅のポリプロピレン製のテープを尿道の下に通して尿道を支え、尿道のぐらつきを抑える手術です。テープを通す位置により、TOT手術(Trans-Obturator Tape)とTVT手術(Tension-free Vaginal Tape)があります
② 切迫性尿失禁
膀胱の筋肉が異常な収縮を生じることで起きます。 まずは過活動膀胱として内服治療を行いますが、薬の効果がなく難治性と判断された場合に下記治療の適応となります。
・ボツリヌス毒素膀胱内注入療法
ボツリヌス菌が作る天然の蛋白質(A型ボツリヌス毒素)から精製された薬を膀胱内に直接注射する治療法です。A型ボツリヌス毒素を膀胱の排尿筋に注入し膀胱の異常な収縮をおさえます。2020年に保険適応となり外来で治療可能です。効果は4-8か月持続し、繰り返し行うことができます。
〈この記事は2025年1月1日時点の情報です〉
- 病院について
-
- 病院長あいさつ
- 基本理念・患者さんの権利と責務
- 沿革概要
- 組織図
- 役付職員
- 職員数
- 病床数
- 診療科別延べ患者数
- 地域別外来・入院患者数
- 予算
- 臨床検査数
- 手術及び麻酔件数
- 画像診断及び放射線治療件数
- 出産児数
- 処方枚数・件数・剤数
- 病理解剖件数
- 血液製剤使用数
- 末梢血幹細胞採取件数
- 医療機関の開設・承認等
- 施設基準届出状況
- 先進医療A・B
- 医療機関の指定等
- 学会認定
- 医療安全管理体制
- 施設
- 基幹・環境整備(屋外環境整備等)
- 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「施設基準」に係る掲示事項
- 病院機能評価の認定について
- 企業等からの資金提供状況
- 病院機能指標について
- 医療安全管理の通報窓口
- 病院情報の公表
- 病院アドバイザリー会議
- 病院監査委員会
- 臨床研究に関すること
- 臨床倫理コンサルテーション
- 医師の働き方改革について
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する情報公開について
- 患者満足度調査
- ご意見について
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- ダイバーシティ推進について
- 院内保育所について
- 病児保育室「Mimi」について
- ネーミングライツパートナー募集
- 子どもの患者さんの権利と約束
- 大学病院改革プラン
- 広報誌・冊子
- 動画コンテンツ
- ソーシャルメディアガイドライン