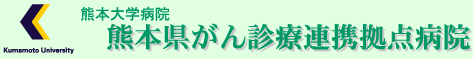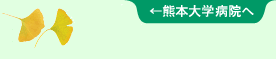|
 |
 |
| 熊本大学病院 |
〒860-8556
熊本市中央区本荘1-1-1 |
| TEL:096-344-2111(代表) |
 |
|
| 「第5回熊本がん治療フォーラム」を開催しました |
 |
座長:倉津教授
(病院長) |
平成20年1月25日(金)午後7時から、熊本市内のホテルにおいて倉津純一教授(熊大病院脳神経外科)を世話人として、熊本県下のがん治療水準を包括的に向上させることを目的に開催されました。大学及び地域医療機関から医師、看護師等の医療関係者及び学生約130名が参加されました。
各講演者の講演概要は次のとおりです。
一般講演「病院臨床における音楽療法の実際」と題して、和田玲子先生(平成音楽大学専任講師)から、終末期医療における音楽療法について、実際に楽器の演奏を交えて発表されました。
音楽療法士は、日本音楽療法学会による認定資格を取得して活動しています。音楽療法とは、音楽の持つ心理的・生理的・社会的働きを用いて、クライエント(対象患者)の心身障害の回復、機能改善、生活の質向上及び行動の変容に向け、音楽を意図的に使用することを指しています。また、音楽療法には、音楽活動させる側面と聴いてリラックスさせる側面があります。
 |
| フォーラム会場 |
治療の道具として使用される理由として、音楽は感性を発散させやすく、美的感覚を満足させ、身体的運動を誘発させるとともに、音楽活動による自己愛的満足をもたらしやすいこと等の多様な特性を有していることが挙げられています。
この療法を説明するため、クライエントの思い出の曲目について、講師によるキーボード及び参加者によるトンチャーム等による演奏があり、会場は美しいメロディーが響き渡り、クライエントに癒しの効果を与えリラックスさせる演出が行われました。このように音楽を通して、音楽療法士とクライエントとのセッションの様子について説明があり、終末期医療における臨床的取り組みの実例が紹介されました。今後も音楽療法による臨床的考察について、更に深めていきたい旨発言されました。
一般講演「熊本県における脳腫瘍の動向」と題して、倉津純一教授(熊大病院脳神経外科)から、脳腫瘍の種類、発生頻度及び外国との罹患率の比較等の統計結果を基に発表されました。
脳腫瘍には、原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍があります。原発性脳腫瘍には、脳実質外にできる髄膜腫等及び脳実質内にできるグリオーマー等があり、脳実質外の場合は治癒可能が大部分ですが、脳実質内に発生した脳腫瘍は治癒困難であります。
熊本県下の脳神経外科の医療施設から、1989年から2006年までの間のデータを集めて分析した結果によりますと、6,794例の脳腫瘍がありました。このうち、原発巣で多いのは、原発性脳腫瘍4,774例の中では、髄膜腫が最も多く、次いでグリオーマ、下垂体腺腫の順になっています。この原発性脳腫瘍は、7割が治癒可能な脳実質外腫瘍ですが、3割が悪性です。また、2,020例の転移性脳腫瘍では、原発巣で多いのは、肺がん、乳がん、大腸がん、胃がんからの転移の順となっており、肺がんは非常に転移しやすく、胃がんは数の割に脳にあまり転移しにくいがんであります。2006年における原発性脳腫瘍は、360人に発見されており、特に髄膜腫の割合が増加しております。髄膜腫の罹患率では、男性に比べ女性の割合が多く、女性は男性の3倍となっております。
最近では、医療機器(CTスキャン、MRI)の普及により、自覚症状もないのに髄膜腫が偶然発見されるようになりました。このような無症候性髄膜腫の増加は、脳腫瘍全体の増加の要因にもなっています。また、オーストラリアで、318人の75才以上の人をMRI検査した結果によると、この中に9人、つまり34人に1人の割合で髄膜腫が発見されました。発見された人は、髄膜腫になっていることに気づかないで、普通の生活を送っていたことになります。長寿の人では、髄膜腫をもっている可能性があることが分かります。
熊本では髄膜腫の発生が多いのですが、米国ではグリオーマの発生が多く、白人男性に多く発見されています。最近、熊本においてもグリオーマが年々増加し、この20年間で2倍に達しておりますが、原因は明らかではありません。特に高齢者のグリオーマが多くなっています。その他に脳の悪性リンパ腫の患者も増えており、リンパ腫がなぜ発生するかは明らかではありません。
小児脳腫瘍の罹患率では、熊本と欧米ではあまり変わりません。しかし小児脳腫瘍のうち、胚細胞腫については、米国やカナダに比べ熊本の発生率が高く、従来より、アジアの子供に胚細胞腫が多いことを裏付けています。
最近、急速に普及している携帯電話の使用と脳腫瘍の発生については、今のところ結論が出ておらず、今後も観察が必要であります。
特別講演「どこが違うか、アメリカと日本の臨床医学」と題して、北野正躬先生(神経学専門医)から、米国で開業医としての医療活動を通して培われた豊富な知識と経験に基づき、日米の医療事情の違いについて、トピック毎にコメントを交えて発表されました。
初めに、米国の医療事情をお話しする上での予備知識から述べていきます。
米国において、医学教育は、4大卒後に4年間の医科大学があり、多様な学生が学んでいます。医師免許を取得するには3階の国家試験があり、取得後は更新制となっています。医師は、専門医の資格取得後、10年後に試験があり、更新しています。開業は、かかりつけ医(プライマリーケア)による数人のグループにより開業されており、24時間診療体制となっています。病院は、開業医がアテンディング・メディカル・スタッフ(Attending Medical Staff)として自分の患者を入院させ、患者と継続した関係が保たれるようなっており、オープンシステムの形態をとっています。病院においては、各専門科目の委員会や感染、教育、資格審査、生命倫理等の委員会の組織があります。また、癌治療に関する腫瘍検討会もあり、医師、看護師、薬剤師等によるチーム医療が施されています。病院の質監視の機関として、医療機関認定組織があります。
【トピック1】脳死と生命倫理について
米国において脳死の判定は、2人の医師が神経学的診察により或条件を満たせば、脳波は必要なく脳死と判定しています。脳死判定後、家族の承諾を得て生命維持装置を外しており、単純化されています。家族が脳死を受け入れない場合には、生命倫理委員会に委ね、家族の説得に当たっています。脳死と臓器移植とは無関係にあります。
【トピック2】医療過誤と訴訟について
「誰でも人は過ちを犯す」という名言があるように、米国では医療過誤は大きな課題であり、医療過誤で亡くなる人が多く、薬剤投与のミスが最大の原因となっております。米国は世界一医療訴訟の件数が多く、人口当たり弁護士数は世界一であります。多民族の国家の米国は、訴訟のほとんどが民事で、損害賠償金が非常に高額になるため、医療過誤保険に入り高い掛金を払って医療保険に入ることになります。従って医療訴訟を防ぐため、医師の意識改革が必要となり、医師と患者の信頼関係が見直されてきました。それには医師の義務として、インフォームド・コンセント、患者の権利、カルテの開示等を行い、患者はできるだけ医師に情報を提供して、両者は協調のうえ見直しが行われています。また、「病人は医療技術のみでは回復せず、医師との信頼関係の下、精神的、心理的サポートなくしては良くならない。」と云われており、ジョンポプキンズ医科大学ウイリアム・オスラー医師は、これをメディカルアーツ(Medical Arts)と呼び、患者に欠かすことのできないものと云われています。
【トピック3】医療費と医療保険について
米国では、過剰診療、保険金の高騰、高齢者人口増等により、医療費が増大しています。従って医療費抑制のため、カリフォルニア州では、保険会社が契約した病院を患者が受診する会員制管理医療保険制度を取り入れましたが、利点もありますが医師の選択や診療が制限される等の欠点もあります。保険制度は個人単位の加入で、未加入者も可成りいます。これらの矛盾を克服するため、医療費の配分が改善され、薬剤費等に関係なく医療従事者の診療技術や医療技術に対する医療報酬に重点が置かれています。
【トピック4】医療費の開示について
米国では、州保険局が作成した公的保険明細書や保険会社の説明書が患者に送られてきます。診療の請求額、保険局が認めた支払額、患者の負担額等が詳細に記載されたものが開示されています。カルテは患者のものとして、インフォームド・コンセント、アカウントビリティー、セカンドオピニオンが必ず書かれるようになっており、医師と患者の信頼関係を示すものであります。ひいては過誤防止や医療の質向上にもつながり、カルテの開示は重要なこととされ、カルテの保存は7〜10年となっております。また、州政府の広報により、行政処分を受けた医師名が全医師に送られ、公開されています。医療過誤、脱税、水増し請求等の原因により、医師の再教育、免許剥奪、病院の診療制限等の行政処分がその内容となっております。
【トピック5】ロスアンゼルス タイムズの新聞記事について
東京の一流大学病院の医療ミスの記事が掲載され、その内容はカルテの改ざん行為は最悪で、また患者に対する傲慢な医師の態度に対する痛烈な批判の記事ありました。米国においても、外国の医療過誤は大きなニュースとして取り上げられていました。
まとめとして、米国の医療制度を参考にするのはよいのですが、慎重にすべきであります。参考とすべきは、患者様へのサービス向上を考えるとき、カルテや医療費明細書の開示、医師免許の更新化、再教育等により、医師の自主的な主導で改善できる面があり、医師自身の意識改革が必要であると思われます。
質の高い医療を行うには、多くの医療費がかかります。医療費は医療技術に対する報酬でありたいものであります。また、医師会だけでなく、患者のロビー活動と協力して、学会が中心でサポートを行い、国や地方の議会へ働きかけていくべきであり、プライマリーケアの医師による患者中心のホームドクターを実現させるべきであります。
癌のチーム医療に関しては、地方医科大学を中心に公・私立病院や開業医師をオープンにして組織化していくこと、及び組織づくりには行政と大学の協力の上で、医師会のリーダーシップが望まれるところであります。
また、日米における医療統計を比較して分かることは、日本は米国に比べ、人口当たりのMRI等検査機器数及びベッド数、平均入院日数、1人当たり平均外来受診回数等を比較した場合に優位にあります。総合的に、日本は医療に恵まれていることがわかります。日本の医療は、WHO(世界保健機関)の評価では、総合点で世界一であり、世界一の長寿国でもあります。しかし、日本は皆保険制度でありますが、1人当たり薬剤費は世界一であり、医療費も高くなってきております。日本の医療制度の改革と国民が安心できる医療には、医師の意識改革のほかに更なる政府の理解と支援が欠かせません。
次回フォーラムの開催時期については、決定次第お知らせいたします。 |
| プログラム |
| 【情報提供】 19:00〜19:10 |
| 『持続性癌疼痛治療剤 モルヒネ塩酸塩水和物徐放性カプセル について』 |
 |
| 【講 演】 19:10〜20:00 |
 |
座長: |
熊本大学大学院医学薬学研究部 |
脳神経外科 |
准教授 |
森岡 基浩 |
|
| 1.『病院臨床における音楽療法の実際』 |
| |
|
平成音楽大学 |
専任講師 |
和田 玲子 |
先生 |
 |
| 2.『熊本県における脳腫瘍の動向』 |
| |
熊本大学大学院医学薬学研究部 |
脳神経外科 |
教授 |
倉津 純一 |
|
| 【特別講演】 20:00〜21:00 |
| |
座長: |
熊本大学大学院医学薬学研究部 |
脳神経外科 |
教授 |
倉津 純一 |
| 『どこが違うか、アメリカと日本の臨床医療』 |
| |
|
神経学 |
専門医 |
北野 正躬 先生 |
|
|